まったく偶然に今みたテレビの人気番組「七人の刑事」(題-終着駅)にポリオの少女が出てきた。定年まぎわの守衛さんが何とかしてクビ切りを延ばそうとして罪を犯す。その背景がポリオの娘を抱えている故だというストーリー。守衛は「この子の治療をしてやらなければならないために、つい人を殺してしまいました」とうなだれる。
こんにちもなおポリオの悲惨さは、殺人ドラマの主題となりうるほどに人々の脳裏にある。もっともポリオ患者自身の描き方はひどく病気の実態とはへだたっていた。もはやポリオを現実に見ることがないからでもあろう。私はその少女ばかりをみてドラマを終わった。じつに、じつに複雑な想いであった。
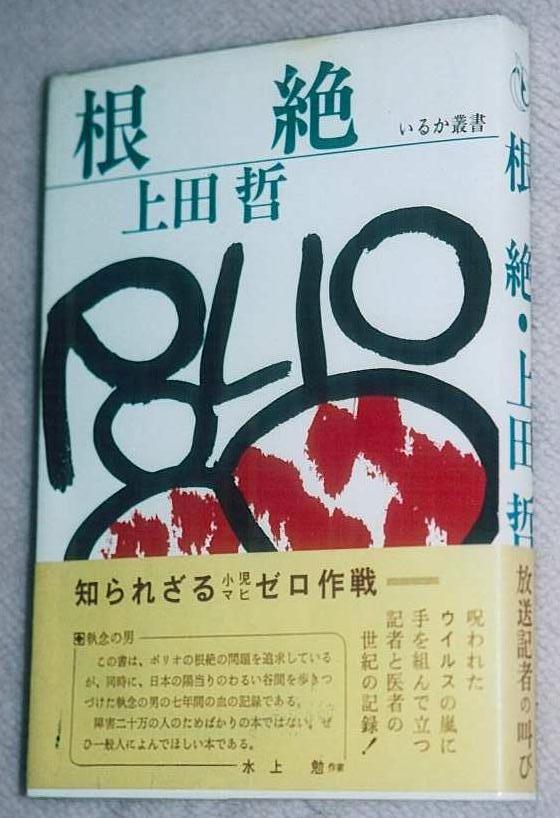
満六年を経たこの間の複雑さを私はどのように正確に報告することができたであろうか。あの激動の中に見えかくれした多くの群像を私は決して歴史的に書こうなどとしたのではない。今夜、私自身がテレビをみながら味わっていたような説明しがたい複雑な感情を、あの時の多くの人々と共にしたいとねがったからである。あの中にいただれにとってもこの〝根絶〟に辿りつかなければ解決することのできない悩みや矛盾があったはずなのだ。
私についていえば、今にきっと、三十六年夏のポリオは大流行ではなかったといえる日が来るものと信じていた。またあの六月十六日「千人突破」の勝負に、一方ではポリオの褶伏をめざし、一方でポリオの猖獗を待った奇妙な、罪に似た感覚をながく忘れることができないでいた。それらの贖罪はようやく今終わったといってはいけないであろうか。
当時の全国の母親にむかってである。
前にむかって私は書こう。ポリオの根絶は終わりではなく出発である。この勝利ははじめてこの国の予防医学の開花を意味する。長い時間をかけてきた「こどもの城」のプランニングが完成し、今私たちの間で具体的に動き出そうとしている。「ゆりかご」以前の母と子の完全健康管理を実現して、十五年後にはハシカも日本脳炎も先天奇型も、すべてのこどもの病気を根絶しようという運動だ。ダイヤルを回したらパトカーや消防車ではなくて、みどり色のこどもの車がオルゴールを鳴らしてとんでくるという健康社会。それをめざしてまた医者と記者のグループが、ポリオの次の感動を味わうために目を血走らせている。だれかがいつかそのことを書くだろう。
世に、いかに情熱を傾けようと、希ったことが実現するのは決して多い例ではない。菲才の私が根絶の日にめぐり遭い、しかもそれを上梓しうることは至幸というべきである。
キャンペーン当時から強く執筆をすすめてくださった現代ジャーナリズム研究所の清水英夫氏、畏友楢橋国武氏の御好意に六年振りに応えるはこびになったのも嬉しいことである。あわせて古く散逸した資料の収集、監修にお力添えをいただいた東大の平山宗宏博土、出版の雑事をすっかり引き受けてくれた雑誌「マスコミ市民」編集部の諸兄姉に深く感謝の意を表したい。
昭和四十二年十月二日
上田哲
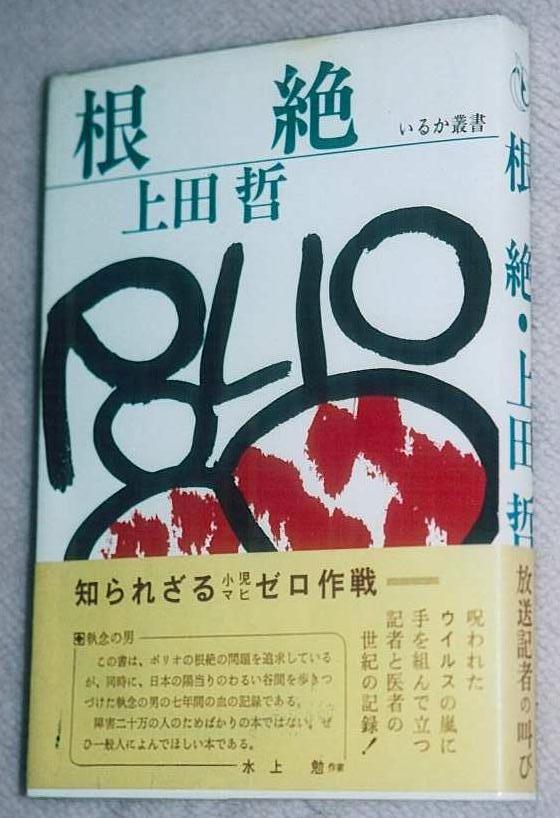 満六年を経たこの間の複雑さを私はどのように正確に報告することができたであろうか。あの激動の中に見えかくれした多くの群像を私は決して歴史的に書こうなどとしたのではない。今夜、私自身がテレビをみながら味わっていたような説明しがたい複雑な感情を、あの時の多くの人々と共にしたいとねがったからである。あの中にいただれにとってもこの〝根絶〟に辿りつかなければ解決することのできない悩みや矛盾があったはずなのだ。
満六年を経たこの間の複雑さを私はどのように正確に報告することができたであろうか。あの激動の中に見えかくれした多くの群像を私は決して歴史的に書こうなどとしたのではない。今夜、私自身がテレビをみながら味わっていたような説明しがたい複雑な感情を、あの時の多くの人々と共にしたいとねがったからである。あの中にいただれにとってもこの〝根絶〟に辿りつかなければ解決することのできない悩みや矛盾があったはずなのだ。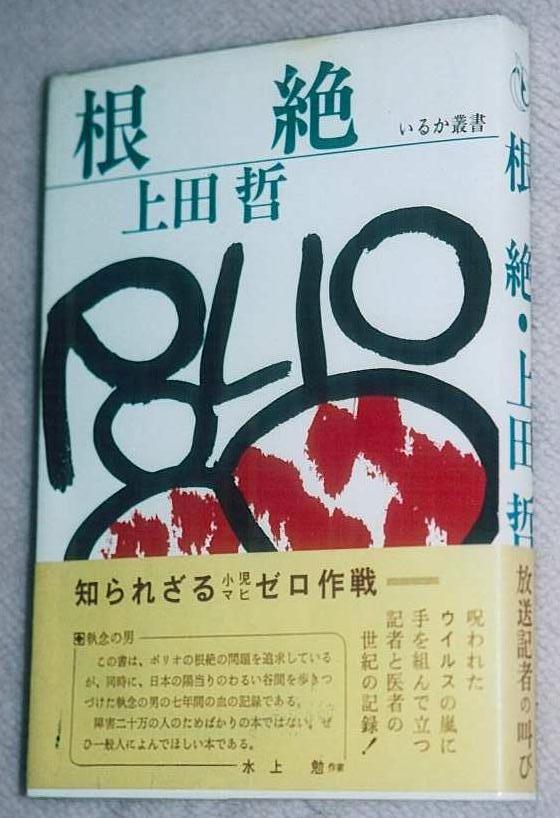 満六年を経たこの間の複雑さを私はどのように正確に報告することができたであろうか。あの激動の中に見えかくれした多くの群像を私は決して歴史的に書こうなどとしたのではない。今夜、私自身がテレビをみながら味わっていたような説明しがたい複雑な感情を、あの時の多くの人々と共にしたいとねがったからである。あの中にいただれにとってもこの〝根絶〟に辿りつかなければ解決することのできない悩みや矛盾があったはずなのだ。
満六年を経たこの間の複雑さを私はどのように正確に報告することができたであろうか。あの激動の中に見えかくれした多くの群像を私は決して歴史的に書こうなどとしたのではない。今夜、私自身がテレビをみながら味わっていたような説明しがたい複雑な感情を、あの時の多くの人々と共にしたいとねがったからである。あの中にいただれにとってもこの〝根絶〟に辿りつかなければ解決することのできない悩みや矛盾があったはずなのだ。